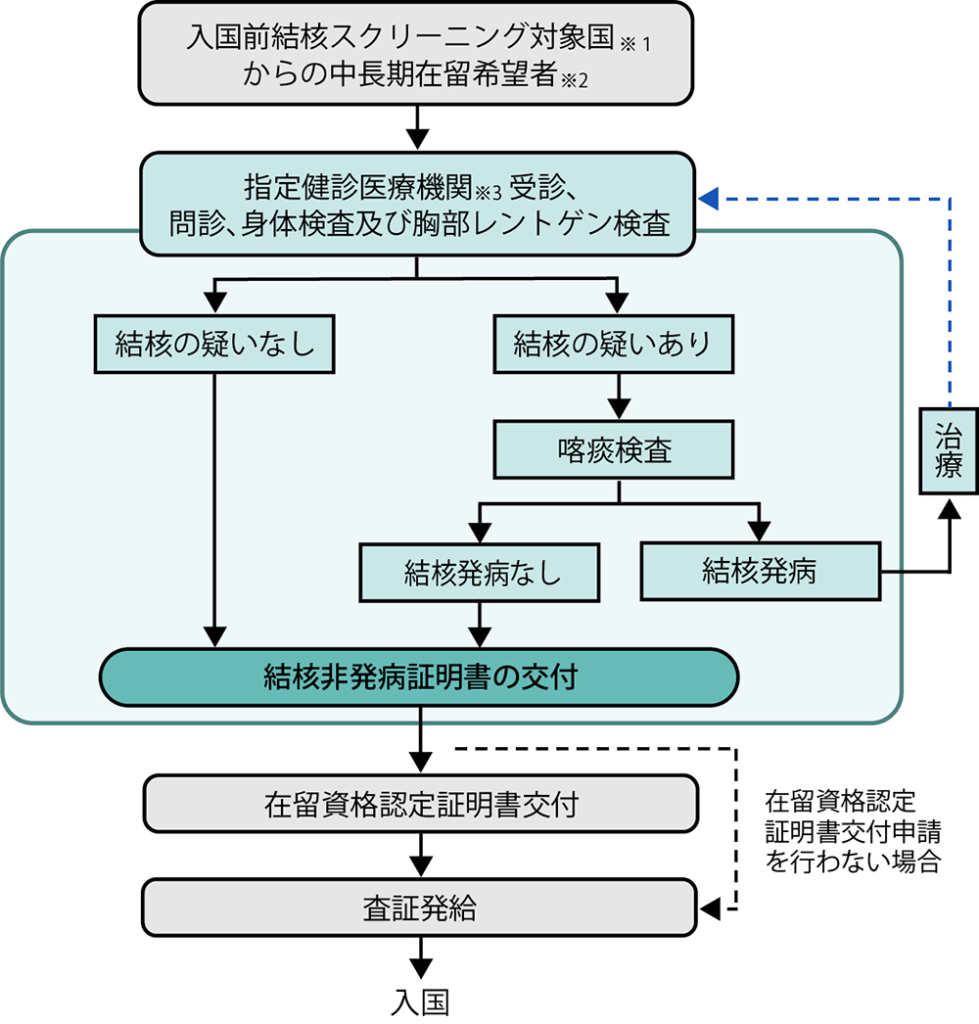近年、ダイバーシティ推進や海外市場開拓をめざす企業にとって、留学生の採用は大きな戦力となっています。
主たる就労系の在留資格としては「技術・人文知識・国際業務」が挙げられますが、この在留資格では、接客などの業務には原則従事できません。一方、「特定活動(46号:本邦大学等卒業者)」の在留資格であれば、一定要件を満たせば接客などの業務にも従事してもらうことが可能となります。
両者の違いを理解し、外国籍従業員に適性に応じた業務に適切に従事してもらうことは、以下の3つのビジネスメリットの獲得に繋がります。
本記事では、まず制度の要件を整理し、そのうえでメリット・留意点を中心に解説します。
制度の要件
- 学歴要件
- 日本の大学(学士)、大学院(修士・博士)、短期大学、高等専門学校、または認定専修学校専門課程を卒業・修了し、学士又は高度専門士の学位を有すること。
- 外国の大学等や、認定済みでない専修学校専門課程は対象外です。
- 日本語能力要件
- 日本語能力試験(JLPT)N1または旧制度の「1級」、あるいはBJTビジネス日本語能力テストで480点以上。
- 大学・大学院で「日本語学」や「日本語教育学」等を専攻した場合は、N1相当とみなされます。
- 業務内容要件
- 単なる指示遂行や清掃・皿洗いに限られない、「日本語を用いた双方向コミュニケーションを要する業務」にも従事すること。
- 大学等で習得した学修成果を活かす企画・開発、翻訳・通訳、教育・研修、営業・広報などの専門性を伴う業務が含まれている必要があります。
- いわゆる「業務独占資格」(医師・弁護士等)や風俗関連業務への従事は認められません。
- 契約形態要件
- 派遣社員、パート・アルバイトではなく、貴社(または同一法人内)の常勤職員としての直接雇用が必須です。
- 転職で所属先法人が変わる場合は、在留資格変更許可申請が必要です。
3つのビジネスメリット
メリット① 即戦力化:バイリンガル+専門性の融合
本制度の対象者は、高度な日本語運用力と専門分野の知識を兼ね備えています。外国人社員へのOJTや社内研修を担当させることで、言語の壁を超えた業務推進が実現します。
メリット② 定着・更新の円滑化:安定的な戦力維持
留学経験を経た人材は日本の社風・マナーに順応済みであり、早期離職やビザトラブルが少なく、長期的な戦力となることが期待されます。
メリット③ 多文化マインドと海外ネットワークの獲得
日本の大学等卒業者は、日本語に堪能であり、また、母国の人脈や現地市場のトレンドを理解しています。多文化チームを編成することで、組織全体のイノベーション創出力が向上します。
定着のための留意点
- キャリアパス設計
- 中長期的なキャリアプランを提示し、モチベーション向上と定着率アップを図りましょう。
- 社内サポートプログラム
- 日本人社員との交流会、多文化理解研修、メンタリング制度、社内相談窓口などを用意し、心理的安全性の高い職場環境を整備することが肝要です。
在留資格「特定活動46号」を活用した留学生の正社員化は、即戦力投資、多文化マインドの醸成、海外ビジネス推進を同時に実現する強力な手段です。
人事部門としては、要件を満たした上で、雇用・在留管理の体制をしっかり構築し、次世代のグローバル人材戦略を推進してください。