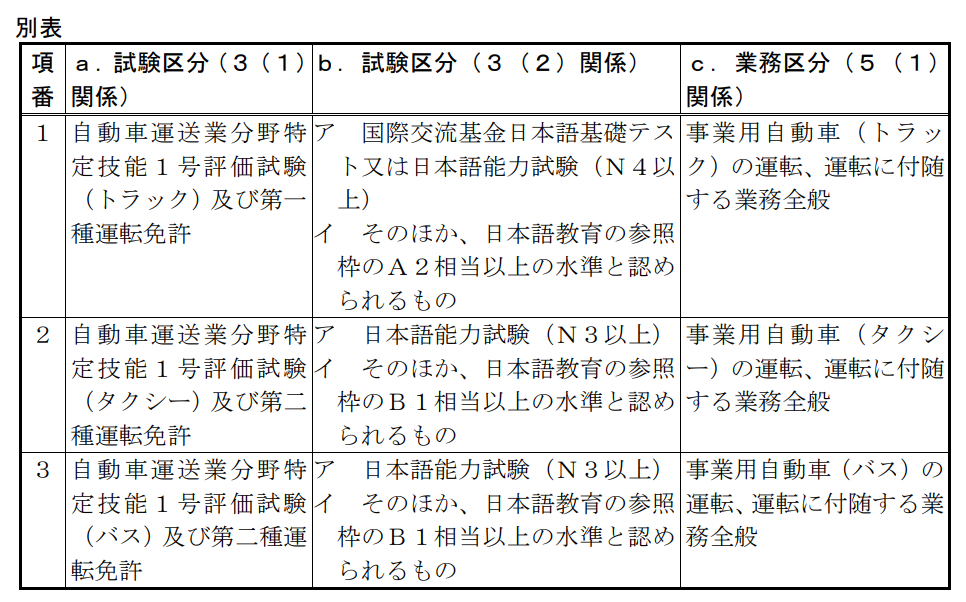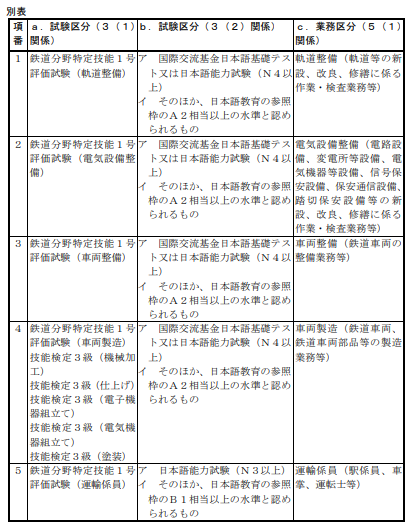近年、宿泊・ホテル業界では、外国人材の採用が増加しています。外国人材の雇用を成功させるためには、いくつかの重要なポイントを理解し、適切に対応することが求められます。
本記事では、宿泊・ホテル業界に特に関連のある在留資格「特定技能」と「技術・人文知識・国際業務」の違い、各業務に従事できる内容について解説します。
1.在留資格「特定技能」と「技術・人文知識・国際業務」の違い
(1)特定技能
「特定技能」は、2019年4月に設けられた新たな在留資格です。特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」があります。いずれも特定の産業分野で働くことが求められます(ただし、1号よりも2号の方が、就労の認められる産業分野は狭い)。
また、特定技能1号には期間の上限が設けられている一方、特定技能2号にはこのような上限は設けられていません。
(2)技術・人文知識・国際業務
「技術・人文知識・国際業務」は、高度な専門知識や技術を有する外国人を対象とする在留資格です。例えば、エンジニア、開発者、研究者、法務、経理、営業、翻訳・通訳、貿易業務等の、専門的な知識を発揮する高度な業務を対象としています。
2.ホテル・宿泊業での従事できる業務の違い
(1)技術・人文知識・国際業務
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人が宿泊業に従事する場合、以下のような業務が考えられます。
- 国際業務:外国人観光客やビジネス客の対応、宿泊施設の国際的なマーケティングやプロモーション、外国語での接客対応やカスタマーサポートなど。特に、多言語対応が求められるフロント業務やマネージャー、国際会議のコーディネーターなどが該当します。
- 翻訳・通訳業務:ホテルの案内資料やウェブサイトの翻訳、外国人客とスタッフとのコミュニケーションをサポートする通訳など。
- 広告・宣伝:宿泊施設のプロモーション活動や広告戦略の立案、実施。
- IT管理:ホテルのシステム管理、ウェブサイトの運営、オンライン予約システムの管理など。
(2)特定技能
「特定技能」の在留資格を持つ外国人が宿泊業に従事する場合、以下のような業務が考えられます。
・フロント業務:チェックイン・チェックアウトの手続き
・接客業務:宿泊客への対応
・清掃業務:部屋の清掃や設備の管理
・その他の現場作業:様々な現場作業全般
「特定技能」であれば、主として現場での業務(例:フロント業務、接客業務、清掃業務)に従事することができます。つまり、現場作業を含む幅広い職務を担うことができます。一方、「技術・人文知識・国際業務」は、より専門的な業務(例:国際業務、翻訳・通訳業務、国際マーケティング、広告・宣伝、IT管理)に従事しなければならず、また、原則として現場作業には従事できません。
このように、従事させたい業務の内容により、適切な在留資格は変わります。その判断は容易ではなく、プロのアドバイスが非常に重要となります。例えば、現場業務に従事させる場合は「特定技能」が適していますが、専門知識や高度なスキルを要する業務には「技術・人文知識・国際業務」が適しています。
3.その他
技能実習制度は、日本の技術や知識を外国人労働者に習得させることを目的としていますが、近年では「技能実習」から「特定技能」への移行が促進されています。これにより、技能実習生は実習期間を終えた後も「特定技能」の在留資格を取得することで、さらに長期間日本で就労することが可能となります。
この変更は、宿泊・ホテル業界においても大きな影響を与えます。技能実習生が「特定技能」へ移行することで、現場での経験と知識を持った労働力が確保され、サービスの質向上に寄与します。
4.まとめ
宿泊・ホテル業で外国人材を採用する際には、「特定技能」と「技術・人文知識・国際業務」の違いを理解し、それぞれの在留資格に適した業務に従事させることが重要です。また、「技能実習」から「特定技能」への移行を活用することで、長期間にわたる安定した人材確保が可能となります。
従事させたい業務内容に基づいて適切な在留資格を選定するためには、専門家のアドバイスを受けることが推奨されます。これらのポイントを押さえて、外国人材の採用と育成を進めていくことが求められます。