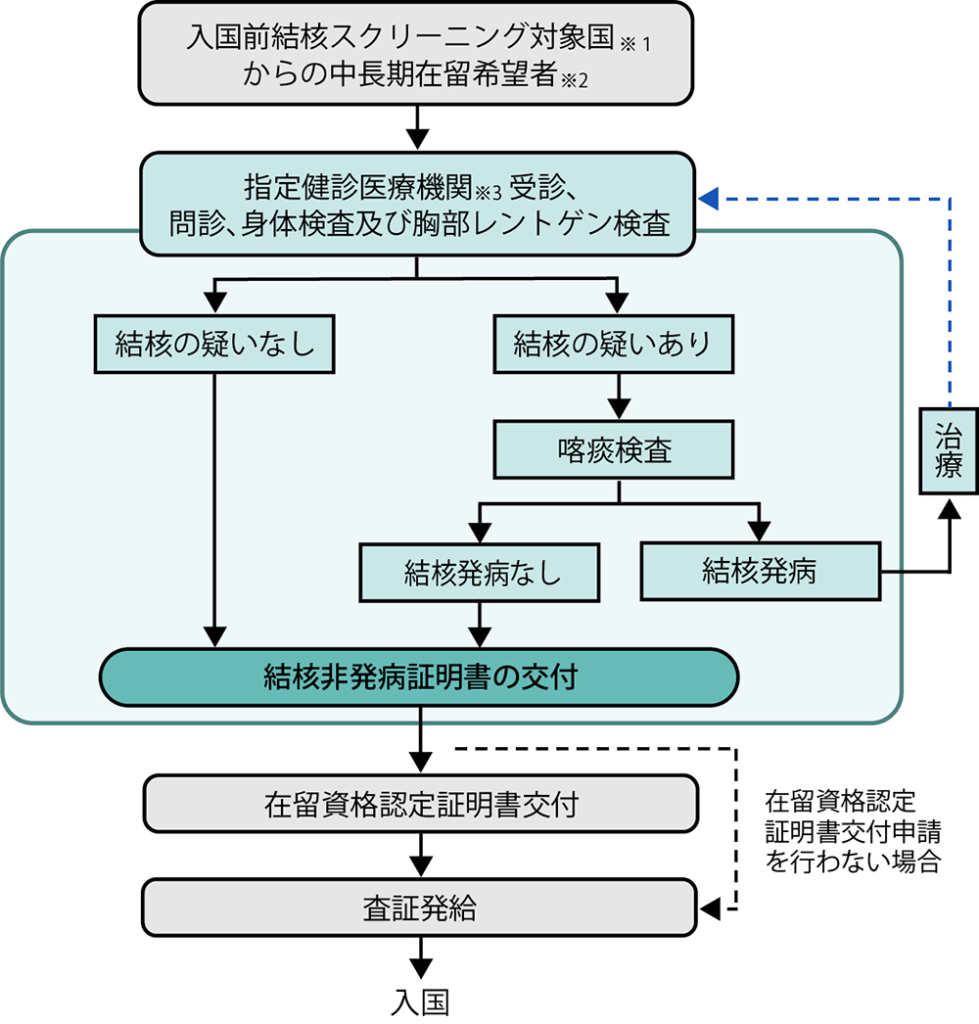令和7年6月に入国在留管理庁より改訂・公開された「特定技能所属機関からの随時届出に関連してお問い合わせの多い事項(Q&A)」は、全170問超の充実した内容で、特定技能外国人を受け入れる企業の人事担当者様必携のガイドです。本記事では、全7章にわたるQ&Aの構成と主なポイントを簡単にご紹介します。
Q&Aの構成
全般事項(Q1-1~Q1-12)
届出の基本ルールの再確認
- 届出の種類:
- 特定技能雇用契約(変更・終了・新規締結)
- 支援計画変更
- 支援委託契約(締結・変更・終了)
- 受入れ困難(行方不明・傷病・1か月以上未実施など)
- 基準不適合
- 支援計画実施困難
- 提出期限・方法:
- 事由発生日から14日以内が原則
- 郵送は「到着日」が基準(消印日ではないので注意)
- 電子届出の事前登録方法も解説
- 届出書の作成・署名:
- 行政書士や弁護士への委任可(委任状を添付)
- 実際に作成した担当者が署名
- 提出先・窓口対応:
- 住所地を管轄する地方局・支局リスト
- 持参・郵送時の身分証明書類の取り扱い
- 提出後の訂正方法
特定技能雇用契約に係る届出(Q2-1~Q2-49)
変更届出(Q2-1~Q2-36)
- 軽微な変更は届出不要のケースを明確化
- 雇用条件書(様式第1-6号)の抜粋提出可・代替書面の要件
- 在留資格認定交付前後の手続き相談フロー
- 雇用契約期間/就業場所/業務内容/労働時間/賃金/健康診断…
→ それぞれ変更事由ごとの届出要件を細かく整理
終了届出(Q2-37~Q2-46)
- 受入れ困難届出との順序:
事由発生時に受入れ困難を先行提出、契約終了後14日以内に終了届出 - 事由別フロー:
- 行方不明時
- 配偶者ビザ等への変更
- 契約満了/重責解雇/個人事業主の死亡 など
新規締結届出(Q2-47~Q2-49)
- 一時帰国後の再締結要件
- 年間所定労働日数・休日日数変更時のまとめ
- 上陸許可時の届出免除条件
支援計画の変更に係る届出(Q3-1~Q3-8)
- 変更箇所のみ提出可:
変更ページ+末尾(機関名称・作成責任者名)のみでOK - 支援責任者・担当者の交代:
就任/退任時の記載要件と添付書類(計画書・履歴書) - 委託形態変更:
- 全部委託⇔自社支援
- 一部委託への切替
→ それぞれに必要な届出種類と資料を具体例付きで解説
支援委託契約の変更に係る届出(Q4-1~Q4-8)
- 対象は「全部委託契約」のみ(一部委託は除く)
- 締結・変更・終了フロー:
- 許可前から委託の場合は届出不要
- 登録支援機関の変更時は「終了」と「締結」の両方を提出
- 個別事例対応:
- 一時帰国による契約終了
- 雇用外国人の退職に伴う届出書記載例
- 契約期間短縮時の要件
受入れ困難に係る届出(Q5-1~Q5-11)
- 終了届出との使い分け:
自己都合退職なら終了届出のみでOK - 添付書類の選定:
- 活動未実施(1か月以上)→様式第5-14号
- 行方不明→様式第5-15号
- その他理由→様式第5-11号
- 特殊ケース:
- 同時提出の可否
- 再入国予定後の届出継続要否
- 合意解除トラブル時の対応指針
基準不適合に係る届出(Q6-1~Q6-9)
- 不適合事由例:
税金・社会保険料の滞納、非自発的離職、法令違反、不正行為、暴行・監禁、手当未払など - 是正後の届出義務:
一時的でも必ず届出、原因と改善経緯は「説明書」にて詳細記載 - 「不正行為」の具体例解説:
暴行脅迫、パスポート取り上げ、虚偽文書使用、届出・報告徴収違反など
支援計画実施困難に係る届出(Q7-1~Q7-3)
- 所属機関からの届出不要ケース:
全部委託している場合は登録支援機関が報告 - 届出要件:
- 計画に沿った支援が実施できなかった場合
- 定期面談等で把握した問題が社内で解決困難→他機関へ相談した場合
- 外国人の「支援不要申出」:
届出不要だが記録の保管義務あり
おわりに
本Q&Aでは、「届出の種類」「提出期限」「添付書類」「提出先」「社内フロー上の留意点」が章立て・事由別に整理されています。ぜひ自社のチェックリストや業務フロー図に落とし込み、ミスなくスムーズな届出運用にご活用ください。
最新の全文はこちらから確認することができます。
特定技能随時届出Q&A(令和7年6月版)PDFダウンロード